魯迅の絶筆
-許広平と内山完造と児島亨- その時刻と経路をめぐって
久保卓哉
はじめに
魯迅が死の前日に書いた内山完造宛の短い手紙がある。「夜中から又喘息が始まったので、今日の十時の約束を果たせなくなった、須藤医師に電話してスグ来てくれるように頼んで下さい」という内容である。これが魯迅の絶筆となった。
この絶筆が許広平によって内山完造に届けられたのは、十月十八日の朝六時頃というのが、これまでの定説であった。
しかし、それは改められなければならない。実際にはもっと遅く、朝七時半から八時の間であろうと考える。そして許広平がどの道を通って大陸新村9号の家から千愛里3号の内山完造の家まで走ったのか、その経路についても明らかにするのが本論の目的である。
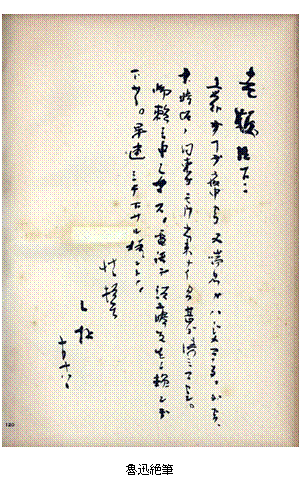
1 魯迅の絶筆
魯迅が内山完造宛に書いた短い手紙は、日付を含めて八行にわたって書かれている。漢字と片仮名交じりの日本語である。
老板几下‥
意外ナ事デ夜中カラ又喘息ガハジメマシタ。ダカラ、
十時頃ノ約束ガモウ出来ナイカラ甚ダ済ミマセン。
御頼ミ申シマス、電話デ須藤先生ニ頼ンデ
下サイ。早速ミテ下サル様ニト。
草々頓首
L拝
十月十八日
内山完造に届けるために魯迅が書き上げるのを待っていた許広平はその時のことを次のように記している。
彼は、朝七時になれば内山先生にお頼みして電話で医者を呼んでもらうように、と言った。私は六時になるまで待って急いで顔を洗い、六時半頃、出かける支度をした。すると、彼は机に向かい、紙と筆を求めると、眼鏡をかけて伝言を書く準備をした。喘息がひどく苦しそうなので、書かないで、私が自分で内山先生に頼みますから、と言ったが返事をしなかった。魯迅はどんな事でも決していいかげんにはしない。だから苦しくてぎりぎりになってもこらえていつものように筆を執った。しかし、書いても字にならず、なんとか頑張って書き出しても一字ごとに書き直してはまた書き直した。半分ほど書いた時私はもう一度、書かないで、後は私がきちんと伝えますから、と言った。それを聞くと彼はひどく不機嫌になった。筆を下に置き、一息ついては、また筆を持ち、続きを書いた。そして長い時間をかけてようやくあの書き付けを書き上げた。それが最後に筆を執った貴重な遺墨となった。 …………… (十一月五日、先生死後二週間と四日の日に記す)
(景宋「最後的一天」『作家』第二巻第二號一九三六年十一月十五日)
魯迅の死後わずか二週間と四日の後に書かれた追憶の記であるだけに、描写は精緻で臨場感に溢れ、目に見えるように迫ってくる。
この手紙を持った許広平は内山完造のもとへ走った。手紙を見た内山完造は須藤五百三医師に電話をして、直ぐに来てくれるようにと頼み、自らは直ぐさま魯迅の所へ駆けつけた。そして呼吸が苦しそうな魯迅の背中を夫人とともにさすり、家から持って来た鶏の卵の油を「お上がりになりませんか」と魯迅に勧め、更に背中をさすっていると、そこに須藤医師がやって来て治療が始まった、というのがその後の経緯である(内山完造「臨終の魯迅先生」『文藝春秋』一九三六年十二月號)。
2 内山完造と須藤五百三の記述
内山完造は許広平が魯迅の手紙を持って来た時のことを次のように記す。
十月十八日午前六時頃、許夫人が来られた。悲しくも今は絶筆となった先生からの寸信であった。
老板
意外なことで夜中から又喘息がハジマツタ。ダカラ十時頃の約束ガモウ出来ナイから甚ダ済みマセン。御頼ミ申ます、電話で須藤先生を頼んで下さい。早速キテ下さる様にと 艸々頓首 L拝
十月十八日
十時には面会の約束があったのである。手紙を見ながら許夫人の話を聞いて居った私は、一種言い難い胸騒ぎを覚えた。
いつもはキチンとかかれる手紙が、今朝は筆が乱れて居る。私は早速須藤医師へ電話して、スグ来て下さる様にお頼みして置いて、其まま駆けつけた。
(内山完造「臨終の魯迅先生」『文藝春秋』一九三六年十二月號)
(内山完造「憶魯迅先生」『作家』第二巻第二號一九三六年十一月十五日)
内山完造は、許広平が家に来たのは「午前六時頃」だと記す。また、増田渉に宛てた十一月三日の手紙でも「十八日の未明に」来た、と次のように記す。
増田先生
魯迅先生の死は丸で夢の様でした。十八日の未明に夫人が来られて例によって寸信を持って来られたが、みると字が乱れて読めない様であった。意外な事から又喘息が出て明日の約束がもう出来ないからよろしく頼む、須藤医師にスグ来て見て呉れる様に頼んで呉れと書いてあった。
(内山完造一九三六年十一月三日増田渉宛書簡 増田渉『魯迅の印象』大日本雄辯會講談社刊一九五六年)
そして電話で呼ばれて駆けつけた須藤五百三医師は「午前六時半」に魯迅の家に往診に行ったと記す。
十月十八日。午前三時喘息の発作が又突然に起こった。午前六時半往診。すぐに跪いて呼吸の手当てをした。患者は顔面蒼白で、冷や汗がしたたり、呼吸は弱々しく、とりわけ短く、か細かった。体温35.7度。脈拍は120前後で、弱い上にしばしば止まった。
(須藤五百三「医学者所見的魯迅先生」附録「魯迅先生病状経過」『作家』第二巻第二號一九三六年十一月十五日)*1
内山と須藤の三件の記述からすると、「六時頃」に許広平が手紙を持って内山の家に来、須藤が「六時半」に魯迅を往診したということになり、矛盾はない。
だがしかし、そこに誤認と矛盾があることは、許広平の「最後的一天」の記述を読めば一目瞭然となる。十月十八日の記述を時間を追って見てみよう。(<午前一時>等の時間の項目は筆者が附けた)
十八日
<午前一時>
魯迅が寝床に上がるのを待って時計を見ると、もう一時だった。
<午前二時>
二時に小便に起きたが、まだ元気だった。
<午前三時半>
また眠ったが、三時半に彼が起き上がるのを見て、私も起きた。よく見ると呼吸が変で、喘息が起こった様子だった。その後ずっと咳きが続いたのだが、咳をするのも困難で、益々息が苦しくなった。魯迅は「二時に起きてから眠れず、嫌な夢を見た」と言った。丁度深夜で、医者を呼ぶわけにもいかず、この喘息は三度目だったが、前の二回よりひどいとは思えなかった。
<午前三時四十分>
苦痛を軽減するために、家に買ってあった喘息の薬「忽蘇爾」を取り出して説明書きを読むと、肺病でも心臓性の喘息でも服用可とあり、急病の場合は一、二時間毎に三回続けて飲んでもよいと書いてあったので、三時四十分に一包を飲ませた。
<午前五時四十分>
五時四十分、三回目の薬を飲むも病状は少しもよくならなかった。三時半に病状が急変してから魯迅は安眠できず、斜めにもたれて休むこともできなかった。終夜身体を曲げ、両手で膝を抱えて座って苦しむ様子はとても辛そうだった。精神的な苦しみなら私にも分かち合えるが、身体の苦しみは彼一人が負っていた。心臓の鼓動が速く、ドンドンという音はそばにいてもよく聞こえた。その時空が明け、彼が右手の脈門に左手を当てているのが見えた。脈が速く打っているのを自分で知ったのだ。
<午前六時>
彼は私に、朝七時に内山先生の所へ行って、電話で医者を呼んでもらってくれと言った。私は六時になるのを待つと急いで顔を洗い、六時半頃に出かける準備をした。
<午前六時半頃>
魯迅は文机の前に座って紙と筆を求め、眼鏡をかけて手紙を書く準備を始めた。息が苦しそうなので、書かないで、私が口で内山先生に頼みますから、と言っても返事をしなかった。彼はどんな事でもいいかげんにしない人だ。だから最も苦しい時でも、なんとかこらえていつも通りに筆を執ったのだが、書いても字にならず、なんとか頑張って書き出しても、一字ごとに書いてはまた書き直した。途中まで書いたとき、私はまた、書かないで、書き残した所は私が口で伝えますからと言った。彼は聞くと不機嫌になり、筆を置いて溜め息を一つつくと、また筆を執って書き続けた。長い時間かかってようやくあの書き付けが出来た。それが絶筆となったあの貴重な遺墨だ。現在は彼の最良の古い友人によって記念として残されている。
(景宋「最後的一天」『作家』第二巻第二號一九三六年十一月十五日)
魯迅から「朝七時になったら内山完造の所に行って電話で医者を呼ぶように頼んでくれ」と言われた許広平は、六時に顔を洗い、内山の所に行く準備をしたのは六時半頃であった。そうした時、魯迅は机に向かって座り、紙と筆を求めて眼鏡をかけ、内山への手紙を書く準備をしたのである。従って六時半頃は、魯迅が手紙を書く準備を始めた時間であって、書き上げたのはそれより後の時間になる。内山が、六時頃許広平が来たと記し、須藤が、六時半に往診したと記したその時間に、魯迅はまだ手紙を書いていなかったのである。
3 児島亨の証言
では、六時半頃に手紙を書く準備をした魯迅がそれを書き終えたのは何時頃で、手紙を持った許広平が内山の家に着いたのは何時なのか。
それを明らかにする上で、これまで顧みられていなかった一つの証言がある。それは一九三三年から一九四五年まで上海の内山書店で働いた児島亨(旧姓中村亨)の証言である。
その証言は泉彪之助編集兼発行の『魯迅と上海内山書店の思い出』(武蔵野文学舎、一九九六年、非売品)に記録されていて、中国では『上海魯迅研究』9(上海魯迅紀念館編、作家出版社、一九九八年)に、張嵩平訳「回憶魯迅和上海内山書店-内山正雄、児島亨、内山芳枝採訪記」として収載されている。
魯迅先生が亡くなられたときのこと、朝八時すぎ千愛里の家の前を掃除していたら許広平先生が魯迅先生の手紙を持ってこられたので、すぐ老板にとどけました。老板がすぐ須藤先生に電話しました。診察の後、須藤先生が店へ帰って来て、「魯迅先生の病気が重いので、松井先生(上海福民医院副院長兼内科医長松井勝冬)、石井先生(石井政吉医師、開業医)に相談したい」と言いました。二人の先生に相談されたはずです。
(『魯迅と上海内山書店の思い出』著者:内山正雄・芳枝、児島亨・静子 協力:鎌田勇夫、西林寿美 編集兼発行者:泉彪之助 武蔵野文学舎
一九九六年 非売品、第十六頁、一九九二年十一月二十八日児島亨証言)
児島亨の証言によれば、許広平が来たのは午前八時過ぎであったという。この八時という時間については、同書第四十六頁の五年後の記録でも、児島亨は重ねて次のように証言している。
許広平先生が紅十字会の会長として日本にこられたときは、私と正雄さんと広島へお迎えに行きました。(前回の証言のように、魯迅が亡くなった前日朝、絶筆となった魯迅のメモを許広平女史から受け取ったのが亨氏だが、そのことを確認した)許広平先生が、「これを老板に渡してください」と言って持ってこられたのです。八時ごろだったと思います。七時前ということはありません。
(前掲同書、第四十六頁、一九九七年九月二十日児島亨証言)
「八時過ぎ」という時間が五年後の証言では「八時ごろ」と変わっているが、児島亨の記憶は八時から動かず、揺るぐことはない。そして定説となっている内山老版と須藤医師の六時説を、「七時前ということはありません」と控え目にだが、キッパリと否定している。それを裏付けるように、児島亨の三男で児島書店を継いだ佐藤明久は、「いつも親父が言っていたことは」と次のように語る。
いつも親父が言っていたのは、許広平先生が魯迅先生の手紙を持って来たのは、開店準備をして店の前を掃いていた八時頃で、これまで言われている六時頃ではない。丁度店の前を箒で掃いている時許広平先生が走ってくるのが見えた。表情を見てただごとではないと思った。許広平先生が「これを老板に」と手紙を差しだしたので、それを受け取ってすぐに店を通って裏口から許広平先生と一緒に内山老板の家に行った。朝、店の前を掃くのは何年も続いた毎日の日課だったから間違いはない。内山老板はなぜ六時と書いたのか不思議でならない。と、いつもこのように言っていました。
(二〇〇五年五月十日証言、二〇〇六年九月十八日筆者再確認)
児島亨は一九三三年二十一歳で上海に渡って内山書店の店員となり、一九三六年のこの時二十四歳であった。彼は上海匯山碼頭に日本郵船の船が着いて本が入荷すると、中国人の車夫と共に大八車を牽いて書店まで運び、中国各地から注文が来ると本を荷造りして、遠くは迪化(烏魯木斉)包頭、昆明、蘭州から、西安、重慶、成都、廣東、廈門、福州、杭州、南京、北京、奉天、石家荘、大連、青島、済南、開封、漢口の地まで、郵便局から送る仕事などをしていた。そして毎朝店の前を掃除することは、日本人店員の日課であった。この光景は、現在の日本のどの町ででも、毎朝普通に見ることができる光景である。
では児島亨が、許広平が来たのは「八時ごろだったと思います。七時前ということはありません」と断言するその時間帯に、本当に店の前を掃除していたのだろうか。児島亨の記憶を裏付ける必要がある。
(附記)ここで気になるのは、泉彪之助氏が記録した児島亨の「朝八時すぎ千愛里の家の前を掃除していたら」という証言で、これだと掃いていたのは店の前ではなくて千愛里の内山完造の家の前になり、児島亨が泉彪之助氏に語った内容と、佐藤明久氏に語った内容とが一致しない。この点を両氏に確かめたところ、泉彪之助氏は「その時私は児島さんは内山書店の前のことを言ったのだと思って聞いた」と明確に答えてくれた。そして佐藤明久氏は「千愛里の家の前は別の人が掃除することに決まっていた。だから父が千愛里を掃除することはあり得ず、掃除したのは店の前であることは間違いない」とやはり明確に答えてくれた(いずれも、二〇〇六年九月十六日、筆者が両氏に電話をかけて確認)。
4 徐民生、陳素珍の証言
現在上海市欧陽路三〇〇弄四号に住む徐民生、陳素珍夫妻は、共に内山書店で働いた経歴を持つ。徐民生は一九一九年生れの八十八歳、陳素珍は一九二四年生れの八十三歳で共に健康で元気である。
二〇〇六年の夏、調査のために上海魯迅紀念館を訪れた筆者の目的を知った張嵐館長と王錫栄副館長は、夫妻の存在を教えてくれたのみならず、二〇〇六年八月二日、外事聯絡日語翻訳・瞿斌、保管部・楽融、攝映員・茅才龍とともに夫妻宅を訪問し取材する便宜を図ってくれた。
その時の様子はビデオカメラを操作する茅才龍によって撮影されたが、ここでは私が筆記したノートをもとに夫妻の証言を再現しておく。
徐民生 私は一九四二年から四三年、二十三歳から二十四歳の間に内山書店で働きました。一九一九年生まれで今は八十八歳です。
陳素珍 私は一九二四年生れで八十三歳です。
徐民生 中国人店員に王宝良と張栄甫(富)がいました*2。張栄甫は共産党員で国民党に捕まりました。日本人店員は二階に住んでいました。三階には本を置いてありました。二階で食事をしていました。台所も二階にありました。内山完造夫妻は一階で食べていました。三階の本の中には『八月的郷村』と『海上述林』がありました。私はそれを読んだからよく覚えているのです。
徐民生
陳素珍 当時私達は十四歳と十九歳の未婚同士でしたが、既に婚約はしていました。
陳素珍 母が内山書店で食事を作っていました。女の日本人の店員は三人いました。
徐民生 貴重な本は夜に三階に運び上げ、朝になって三階から下ろしました。
陳素珍 母は名前を呉天英といい、十数年にわたって内山書店で食事を作りました。子供だった私はいつも母について内山書店に行き母の手伝いをしました。その関係で私も内山書店で働くようになったのです。母は日本人にも中国人にも老板にも皆同じ食事を作っていました。一九三二、三三年の頃、九、十歳の頃、私は内山の千愛里の家の掃除もしました。奥さんも内山も自分の子供のように私を可愛がってくれました。
徐民生 本を買った人が住所を書いて行くので、私はその家に本を配達するのが仕事でした。配達の時は自転車で配達していました。お客は日本人が多く、家に配達して持って行っても、日本人は私を平等に扱ってくれて礼儀正しかった。偉ぶった態度はなかった。
ある時、中国人と中国人とが喧嘩をしたことがありました。その時内山は二人を呼んで「お前は中国人、お前も中国人。中国人と中国人が喧嘩しても良いのですか」と言って二人を仲直りさせました。
広告は老板が書きました。老板は中国語が上手で、私たちには「小郎」と呼んで、王宝良には「王さん」と日本語で呼んでいました。
老板はみんなを平等に扱ってくれました。少しも「老板」という態度はなかった。いつも微笑んでくれました。老板には『上海的早晨』という本があります。
書店は八時に開いて午後五時まででした。
私は毎朝七時半に出勤しました。出勤して二階に上がることがありましたが、その時日本人は皆一階に居ました。
一番忙しかったのは、日本からの船が「滙山碼頭」に着いた時で、荷を下ろしに四人で行きました。一人は中村亨(児島亨)で、中村亨は車で行きました。三日に一度船が着きました。店は、四川路、呉淞路、山陰路に三店ありました。
陳素珍 母は食事を作っていました。朝六時に内山書店に行って朝食を作り、朝食を作り終えると、昼食と夕食を作る食材の買い出しに出かけました。私はそのまま店に残って内山書店の手伝いをしました。
徐民生
陳素珍 内山書店では朝七時から朝食で、十二時が昼食、十七時が夕食でした。朝食の時は三人の日本人が二階で食べ、内山夫妻は一階で食べました。昼食の時は十三、四人が二階で食べ、夕食は朝食と同じく五人で食べていました。
陳素珍 七時から七時半までが朝食時間で、私は七時半に後片づけをしました。
魯迅が内山書店で食事をすることがありましたが、二階から食事を運ぶと、魯迅はいつも「ありがとう」と言ってくれました。
内山の紹介で日本人の家のお手伝いさんをしたことがありました。
徐民生 私がなぜ内山書店で働くようになったかと言うと、妻(陳素珍)の母の紹介でした。初めて老板に会った時、老板は私の学歴を聞きました。私は「高郵県立中学」を卒業していました。
徐民生
陳素珍 魯迅がよく内山書店に来ていましたが、その時老板は「中国客人来了」と言っていました。特に魯迅だとか許広平だとか言いませんでした。
これがその全容である。取材は午前九時半から十時五十分まで一時間二十分に及んだが、夫妻は快く四人を室内に招き入れてくれ、よく冷えた西瓜をご馳走してくれた。
この証言によって内山書店の朝の時間帯が明らかになった。日本人店員は七時から七時半まで二階で朝食をとり、七時半になると一階に下り、同時刻に出勤してきた中国人従業員と共に、八時の開店の準備をしたのである。
従って児島亨が朝店の前を掃いていたのは七時半から八時の間で、その時に許広平が来るのを見たことになる。そう考えてよい。
5 魯迅が手紙を書き上げるまでの時間
魯迅の家から内山書店まで、もしくは千愛里の内山完造の家までは三分以内で着く。児島亨が言う八時頃に許広平が手紙を持って来たとすると、魯迅は六時半頃から書く準備を始め、書き終えたのは八時前になる。魯迅は一時間以上かけて内山への手紙を書いたことになる。
文面が四行で、宛名と署名と日付とを含めてもわずか八行しかない短い手紙を書き終えるまで、一時間以上もかかることはあり得ない。そう考えるのが普通であろう。
しかしこの日の朝、魯迅の容態はそれだけの時間を要した。それは前掲許広平の「最後的一天」の<午前六時半頃>の記述を読めば分かる。そこには、息苦しさに堪えながら、書き終えるまで決して投げ出さない魯迅の鬼気迫る姿が描かれている。魯迅の精神は、死期迫る肉体の限界を凌駕していた。
これについては魯迅研究家で医学者でもある泉彪之助が、既に次のように問題を提起している。
須藤五百三と内山完造の記載いずれも、須藤五百三が魯迅を診察したのは、午前六時半ごろとなっている。この児島氏の証言はそれと一致しないが、許広平夫人の記録<最後的一天>を見ると、発作が深夜起こったため医師を呼ぶことができず、朝七時になったら内山完造に連絡を頼むことにして、六時半から魯迅が手紙を書きはじめたがなかなか進まなかったとある。実際の診療は、通説より遅く行われたのではないだろうか。
(同上『魯迅と上海内山書店の思い出』第十六頁「一九九二年十一月二十八日児島亨証言」章)
このたびの上海での調査により、泉説は極めて正論で、拙論はそれを支持し補充する結果となった。
魯迅が内山完造に伝えたい一心で、最後の力を振り絞って筆を執ったことに、夫人ですら侵犯することができない、魯迅と内山の友情の深さと固さとを感じざるを得ない。夫人を通しての伝言ではなく、自ら筆を執って礼を尽くして書いた魯迅の誠意に感動せざるを得ない。そして横で見守る夫人の魯迅への敬意と深い愛を感じざるを得ない。夫人の焦燥は如何ばかりであったか、それは容易に想像がつくからである。
6 許広平の経路と「最後的一天」
児島亨の証言は、絶筆が内山完造に渡るまでの経路をも明らかにする。許広平から内山完造へではなく、許広平から児島亨へ、そして児島亨から内山完造へという経路である。そしてまた、魯迅の家から直接に千愛里3号の内山の家にではなく、大回りをして内山書店の入口から店内を通り、裏口へ抜けて内山の家へ、という経路である。
ではなぜ許広平は家の西側にある千愛里の道をまっすぐ南下せずに、わざわざ八軒もの家の前を東に出て、大きく西回りになる施高塔路を南下したのであろうか。
今の魯迅故居の西側には高い壁があって千愛里に抜けることはできない。その壁が当時からあったのであれば西へは行けず、東側の施高塔路を南下するより他はない。この壁は一九三六年の当時からあったのだろうか。
この疑問を解決してくれたのは、このたび様々なことを教示してくれた王錫栄副館長であった。氏はこれまで数々のすぐれた魯迅研究の業績を残しているが、過去に大陸新村の魯迅の故居周辺の立地環境を詳しく調査したことがあったと言う。氏によると、南側向かいの建物(現在:山陰路一二四弄二四号~四三号)は一九三六年より以前には無く、千愛里の内山の家と内山書店の裏口へは、魯迅の家から真っ直ぐに行くことができた。だが一九三六年に南側に建物が建ち、千愛里に続く路地との間に壁が出来て、現在と同じ周辺環境になったと言う。その壁は現在上海魯迅紀念館に展示されている出棺の日の写真に写っている。従って許広平は施高塔路を南下すべく、家を出て東に向かったのである。

魯迅の柩を運ぶ霊柩車 車の後ろに壁が写っている
上海魯迅紀念館展示写真(写真/筆者)
許広平の道順を再現してみよう。
許広平は家を出ると東の施高塔路に出て南下し、大きく西に曲がる道をたどった。そして、内山の家がある千愛里への路地を北に向かって入ろうとしたが、その時前方に、書店の前を掃く児島亨の姿を見つけ、千愛里へ入るのをやめて、真っ直ぐに児島亨の所に向かった。そして手紙を示しながら「これを老板に渡してください」と言った。手紙を受け取

った児島亨は、店内を通り抜けて裏口に出、すぐに内山完造に届けた。
だがこの経路は許広平の「最後的一天」に記されていない。許広平はただ次のように記しているだけである。
早朝で書店はまだ開いていなかった。内山先生の家の前に行くと、先生は既に出て来ていた。慌ただしく、電話をかけるように頼み、私は急いで家に戻った。間もなく内山先生も来て、自分で薬を飲ませてくれ、背中を長いこと撫でてくれた。魯迅は内山先生にとても苦しいと言った。私たちはそれを聞いてとても辛かった。
清晨書店還沒有開門、走到内山先生的寓所前、先生已走出來了、匆匆的託了他打電話、我就急急地回家了。不久内山先生也親自到來、親手給他藥吃、並且替他按摩背脊很久。他告訴内山先生説苦得很、我們聽了都非常難受。
(景宋「最後的一天」『作家』第二巻第二號一九三六年十一月十五日)
この記述の中に「早朝で書店はまだ開いていなかった(清晨書店還沒有開門)」とあるのが気にかかる。この表現からすると、許広平が手紙を持って出たのは八時前ではなくて「清晨(夜明け、早朝)」だったと読みとることができるからである。
だがそれでは、この記述の直前にある、六時半頃に魯迅が机に向かって手紙を書き始め、最後の力を振り絞って長い時間をかけて書き上げたことと齟齬が生じる。「清晨」に書店に届けたのであれば、魯迅は元気な時と同じく数分も要しない短時間で手紙を書き上げたことになるからである。
しかも、以上で検証した児島亨の証言と、徐民生、陳素珍の内山書店開店時間の証言と、泉彪之助の証言記録と、そして佐藤明久が父から聞いた証言等の個々の事実は、客観性を持たなくなってしまう。
従って許広平が記した「清晨」は、語義通りの「早朝」、つまり「六時半頃」ではなくて、書店がまだ開店していない時間帯である「八時前」までの「朝早い時間」を意味していると読むべきであろう。
おわりに
これまで考証してきたことからすると、許広平の「最後的一天」の記述の裏には、次のような内容が隠れていると考えざるを得ない。傍線部がそれである。最後にそれを記しておく。
清晨書店還沒有開門、那時内山書店的職員正在打掃。他看到我手裏就帯我去内山完造家。走到内山先生的寓所前、先生已走出來了、匆匆的託了他打電話、我就急急地回家了。
早朝で書店はまだ開いていなかった。その時内山書店の店員が店の前を掃いていた。彼は私の手の中の物を見るとすぐ私を連れて内山完造の家へ向かった。内山先生の家の前に行くと、先生は既に外に出て来ていた。私は慌ただしく、電話をかけて下さいと頼み、急いで家に戻った。
(附記)上海での調査をもとにして拙文を書くに当たっては、張嵐、王錫栄、秦海琦、蒋雅萍、瞿斌、楽融、茅才龍、李玉英(以上上海魯迅紀念館)及び徐民生、陳素珍(元内山書店労働者)、林錫珪(現内山完造旧居所有者)及び泉彪之助、佐藤明久の各先生から誠意溢れる助言と協力を得た。ここに心から感謝の意を表したい。
【注】
*1 須藤五百三の「魯迅先生病状経過」は、『作家』所載の中国語の文章より他に見ることができない。北岡正子「『上海日報』所載 須藤五百三「醫者より觀たる魯迅先生」について」(『野草』第71号2003.2.1)に指摘がある。
*2 徐民生(内山書店元配達員)は、「張栄甫」の「甫」は「富」かも知れない、よく憶えていないと話したが、『季刊鄔其山』第九号1985年33頁に掲載する内山書店前写真の後列の人物説明の中に、「栄甫」とある。なお、周国偉・彭曉著『尋訪魯迅在上海的足迹』上海教育出版社1987年は「張栄富」(18頁)と記し、同じ著者周国偉の近刊書『魯迅与日本友人』上海書店出版社2006年も「張栄富」(229頁)と記す。「甫」か「富」か、判断がつかないが、徐民生はこの時、「栄甫」と先に言い、その後に「栄富」かも知れないと言った。その時の記録が筆者のノートに残る。